「……ん……」
「!団長!」
「…こ、こ は…?」
目を開けた。ぼんやりとした視界に映ったのは打ちっ放しコンクリートの無機質な天井だった。…ここは、どこ?私、なんでこんな所にいるの?……そうだ。私、学校から帰る途中でトラックに跳ねられて…じゃあここは病院?でも病院にしては変な感じの建物だ…
「起きたか」
「うん。でもまだはっきりと目覚めてはいないみたいだけどね」
「……だ、れ?」
体中が痛む。声が巧く出てこない。身体を動かそうとすればその度に引き裂かれるような、燃えるような痛みに襲われる。…ぼやけ気味の私の視界に写ったのは黒髪の男性だった。
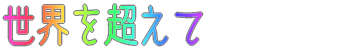
「目は見えるか?オレの声は聞こえるか?」
「…見え、ます…声も、」
「そうか」
艶のある低音はの耳に心地よく沁み込んだ。
漸くはっきりと見えるようになったの目には端正な顔立ちをした黒髪の男性と、中性的な印象の金髪の男性が写る。
視線だけで辺りを見回せばまるで廃墟みたいな荒れ果てた部屋だった。
「名前は?」
「……、です」
「、か…。、自分がどうして此処にいるか、判るか?」
「どうして、って……私、車に跳ねられて…ここ、病院じゃ……」
「……団長」
「あぁ」
車に跳ねられた、という言葉を聴いた途端、二人は目を見合わせて驚いた顔を浮かべた。
……此処は、病院じゃないの?私、いま何処にいるの?貴方達は、誰?
の瞳に困惑の色が浮かぶ。
金髪の青年はベッド脇に腰を下ろし、と視線を合わせると諭すような優しい声で言った。
「…あのね、よく聞いて。いい?君、いきなり空から降ってきたんだよ」
「…そ、ら…から?」
「そう。その様子だと…自分の今居る状況、判ってない?」
「…はい…」
空から降ってきた、ってどういう事?ねぇ、誰か教えて。私は今、何処にいるの?
が意識を失う直前に見た物は近づいてくるトラックだったはず。
それならば、目が覚めるべき場所は病院のはずなのだがどうも病院という雰囲気ではない様だ。
かといってここが死後の世界、という訳でもないらしい。
「…君ね、空から降ってきたんだ。…クルタ族って訳でもなさそうだし、君酷い怪我してたから」
「クル、タ族…?」
「その服は何処の民族衣装?」
「…これ、は…私の通ってる学校の、制服で…」
民族衣装、って…普通に何処でもあるありふれたブレザーの制服なんだけど…それにクルタ族、って…?
クルタ族、という言葉に聞き覚えはない。
否、正確に言えば何処かで聞いた事があるような気がしたが、記憶を必死で手繰り寄せてもその答えは出てこなかった。
「学校?」
「……はい」
「…団長、団長の考えでビンゴっぽいよ」
「そのようだな……」
二人は顔を見合わせて何やら話をし始めた。
はといえば未だに自分の置かれている状況が把握しきれていない。
空から降ってきた、と告げられ、ありふれた制服を民族衣装と言われたのだから。
「…、いいか、落ち着いてよく聞くんだ。」
「はい……」
「…恐らく、お前は時空を飛ばされて此処へ来た。オレ達の知る限り、が着ているような服は見たことがないしな…」
「じく、う……?じゃあ、」
「文献でしか見た事がないが…恐らく車に跳ねられた事が切欠となって飛ばされたのだろう。…恐らく此処はが居た世界とは別次元だろうな…」
「別、じげ…ん?」
いきなり話が飛躍しすぎてて、理解が出来ない。
何の脈略もなく、此処が異世界だ、なんて言われて誰が信じるというのか。
確かに此処は病院という雰囲気でもないし、目の前の二人だって医者っていう雰囲気でもない。
だからといって、此処が異世界だという答えに結びつけるのは余りに安易過ぎる。
…ねぇ、本当に私は今何処にいるの?
は心の中で誰に問うでもなく疑問を浮かべた。
「あぁ…兎に角今は怪我を治す事を考えろ。」
「…はい……あの、」
「オレはクロロだ。こっちはシャルナーク」
「クロロさん、と…シャルナーク、さん……」
「…ゆっくり休め。食事は後で持ってこよう」
「……はい」
二人の青年が部屋を出て、部屋は一気に静まり返った。
は身体を起こす事も出来ずにただベッドから窓の外を眺めていた。
窓の外に見えるのは、廃墟のようなビル群と、とても大きな月だった。
(せかいをこえて、であえたきみへ)